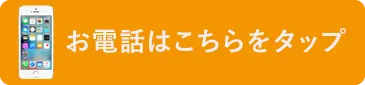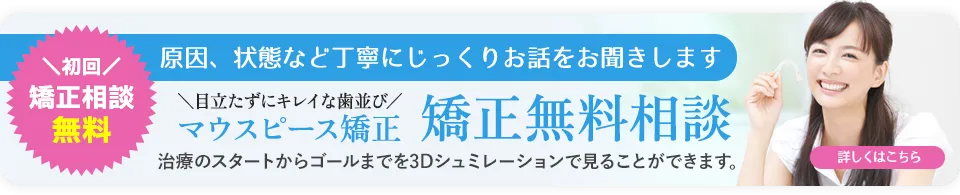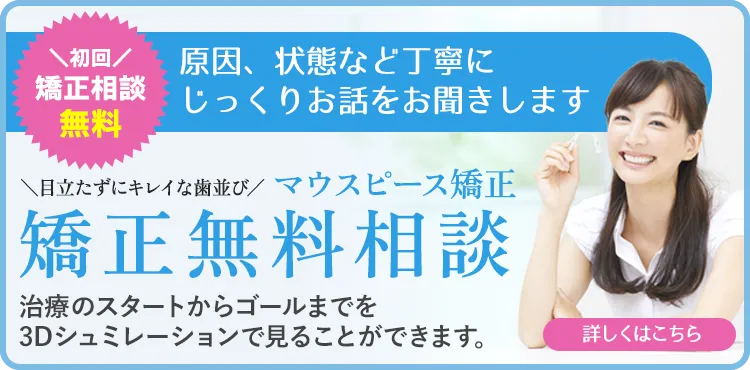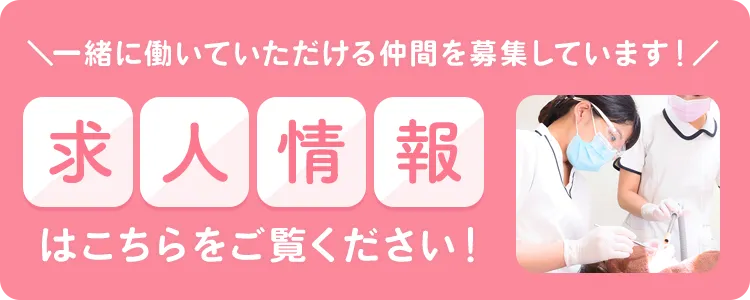こんにちは!大阪府八尾市の歯医者、ママとこどものはいしゃさん認定医院のもりかわ歯科です。
「なんだか子どもの歯並びが気になるけど、矯正って高いのかな…」
「小児矯正に保険はきくの? それなら費用を抑えられるのかな…」
「支払い方法に選択肢があるなら、もっと気軽に相談できるかも…」
こうしたお悩みをお持ちの方は少なくありません。
費用のこと、保険の適用、治療にかかる期間など、小児矯正には知りたいことがたくさんありますよね。
実は「矯正=とても高額でハードルが高い」というイメージは、必ずしも正しいわけではありません。
保険が適用されるケースもあれば、支払い方法を選ぶことで家計の負担をコントロールすることも可能です。
本記事では子どもの歯並びや歯列矯正にまつわる疑問や不安をできる限り取り除けるように、基礎知識やリスク、費用面でのポイント、支払い方法についてわかりやすく解説します。
「ママとこどものはいしゃさん」として小児歯科を専門に多くのご家族をサポートしているもりかわ歯科の視点からお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください!
Contents
この記事を読めば分かること
- 小児矯正の適切な開始時期がわかる
- 小児矯正の費用相場や保険適用の有無について理解できる
- 医療費控除や支払い方法の選択肢を知ることで費用の不安が減る
- 放置した場合に考えられるリスクと、矯正のメリットが分かり、前向きに検討できる
小児矯正はいつ始める?そのベストタイミング

小児矯正は早いほど良い?その理由とは
小児矯正をスタートする年齢について「何歳がベスト?」と悩まれる方は多いでしょう。
じつは「この年齢でないといけない」という絶対的なルールはありませんが、多くの歯科医師は「できるだけ早め」をおすすめしています。
これは、成長期のお子さまのあごや歯並びが変化しやすく、早期に矯正を行うことで抜歯のリスクを減らせるうえに、顎の成長を正しい方向に導きやすいからです。
目安となる時期
6〜7歳ごろ(第一期矯正)
乳歯と永久歯が混在し始める時期です。
あごの成長バランスを整えたり、歯がきれいに並ぶためのスペースを確保したりする治療を行うことが多いです。
12歳前後(第二期矯正)
永久歯がそろってくる時期です。
本格的に歯を動かすワイヤー矯正やマウスピース矯正へ移行しやすくなります。
お子さまの成長速度や歯並びの状態を見極める
一方で、お子さまの成長スピードや歯の生え替わり具合は人それぞれです。
乳歯の段階ですでに噛み合わせのずれが大きい場合や、出っ歯・受け口の傾向が強い場合は、もっと早い段階での対処が必要なケースもあります。
「放っておいてもいずれ自然に治るかもしれない」と考える方もいますが、現状を正確に把握するためには歯科医院でのチェックがおすすめです。
検査によって必要な治療や最適なタイミングがより明確になります。
小児矯正の費用相場と保険適用のポイント
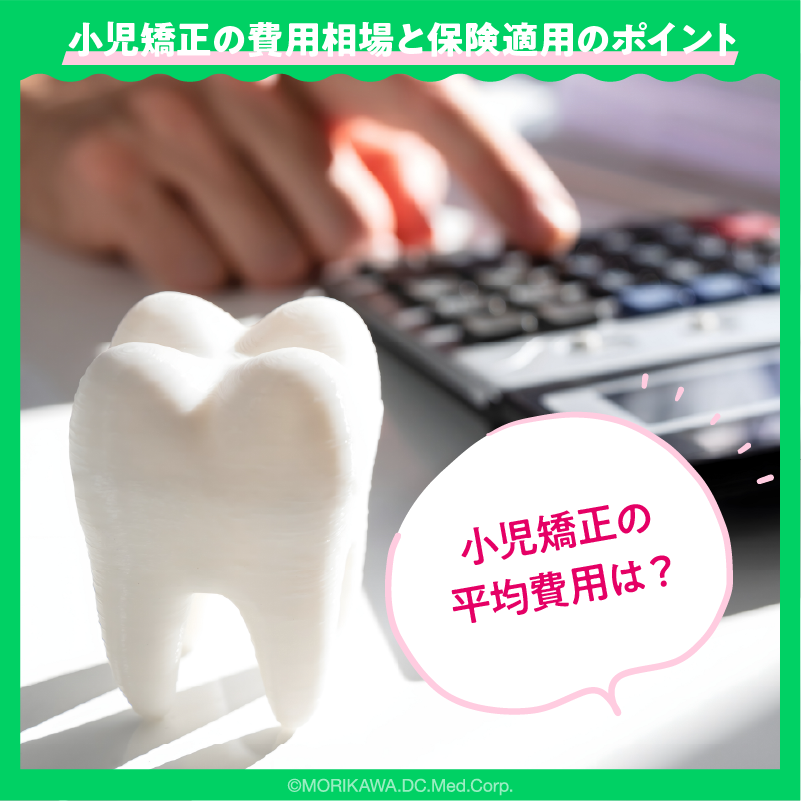
小児矯正の平均費用
子どもの矯正費用は大人の矯正よりも安くなるイメージを持つ方もいますが、実際には治療の内容・期間・装置の種類によって大きく変わります。
一般的には数十万円から100万円前後の費用がかかることが多いです。
第一期矯正(乳歯〜混合歯列期)
費用目安
30万〜60万円程度
内容
プレートやマウスピースなどを活用し、顎の成長を促す・抑制するなどの治療
第二期矯正(永久歯が生えそろう時期)
費用目安
50万〜100万円程度
内容
ワイヤー矯正やマウスピース矯正(インビザラインなど)を使用し、本格的に歯列を整える
もちろん歯科医院ごとに料金体系が異なるため、カウンセリング時に詳しく聞いてみるのが安心です。
保険適用となるのはどんなケース?
小児矯正が保険適用になるケースは、実はごく一部の特例に限られます。
主に顎変形症や唇顎口蓋裂などの診断を受け、矯正治療が「顎口腔機能の改善」のために必要と判断された場合などです。
通常の不正咬合(歯並びや噛み合わせの悪さ)に対する矯正治療は、美容や機能改善の面が強いとみなされるため、保険適用外(自由診療)となるのが基本です。
「小児矯正は保険がきくから安い」と思い込まず、まずは診断を受けて保険適用の可否をしっかり確認しましょう。
混乱しやすい点:医療保険や助成制度との違い
医療保険(国民健康保険、社会保険など)による適用とは別に、自治体や学校等が行っている助成制度・補助金などがある場合もあります。
これは地域によって異なるため、住んでいる自治体の情報をチェックしてみてください。
また、医療費控除(後述)と保険適用は別の仕組みなので、併用できるかどうかは条件を確認する必要があります。
小児矯正は医療費控除の対象?支払い方法も解説
小児矯正は医療費控除の対象になることが多いです
医療費控除の基本条件
医療費控除とは、1年間(1月〜12月)で支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税の負担を軽減できる制度です。
目安としては年間で合計10万円以上(または所得に応じた計算式)を支払ったときに申告の対象となります。
お子さまの矯正治療費は高額になりやすいため、この基準を超えるケースは少なくありません。
対象となる費用
子どもの矯正装置代や調整料、検査費用、さらには通院にかかる交通費なども含めて計算できます。
大切なのは、お子さまの咬合機能を改善するための治療と認められることです。
審美目的のみと判断される場合は控除の対象外になる可能性があるため、不安なときは税務署やかかりつけ歯科医に相談しましょう。
審美目的には適用されない場合も
大人の矯正治療では審美面が主たる目的とみなされると適用外になるケースがありますが、子どもの成長をサポートするための矯正は多くの場合、医療費控除の対象に含まれやすい傾向があります。
確実に対象になるかどうかはあらかじめ担当の歯科医師に確認するか、税務署で詳細を聞いてみると安心です。
一括払いだけじゃない。さまざまな支払い方法
現金やクレジットカードで支払う
「大金を一度に支払わなくてはならないのかな…」と心配される方は多いかもしれませんが、まとまった金額を現金で用意できる方はもちろん、クレジットカードの利用も可能です。カードの分割払いやリボ払いを活用すれば、負担を分散させることができます。
デンタルローン(医療ローン)という選択肢
歯科治療費専用のローンである「デンタルローン」を利用する方法もあります。
月々数千円からの返済が可能になるため、無理なく通院を続けやすくなるでしょう。
申請には審査が必要ですので、検討している場合は早めに歯科医院やローン会社に問い合わせてみてください。
医院独自の分割払いも
医院によっては独自の分割払いプランを用意しているところもあり、矯正治療にかかる費用を数回から十数回に分けて支払える場合があります。
利子の有無や支払い回数は医院によって異なるため、事前にしっかりと確認しましょう。
お子さまの矯正は時間がかかる治療なので、一人で悩まずに気軽に相談してみることが大切です。
きっと家庭の状況に合った方法を一緒に見つけられるはずです。
子どもを矯正しないとどうなる?放置が招くリスク

歯並びの悪さが与える影響
「歯並びは自然に治るかも」と思って放置してしまうと、後々さまざまなリスクが生じる可能性があります。
代表的なものとしては、虫歯や歯周病リスクの増加、咬み合わせの偏りによる顎関節への負担、そして見た目や発音面に関するコンプレックスなどが挙げられます。
虫歯や歯周病リスクの増加
歯が重なり合う部分が多いほど清掃が行き届かず、汚れやプラークがたまりやすくなるため、虫歯や歯周病のリスクが高まります。
特に幼少期から虫歯を繰り返すと、将来的に歯の健康を損ないやすくなる点に注意が必要です。
咬み合わせの偏りによる顎関節への負担
噛み合わせが悪いと顎関節や咀嚼筋に過度な力がかかり、顎関節症などのトラブルを引き起こす恐れがあります。
成長期にこうした負担が続くと、あごや頭蓋全体にも影響を及ぼすことがあるため、早めに対策を検討したほうがよいでしょう。
コンプレックスや発音への影響
歯並びの乱れは見た目の印象だけでなく、発音や口元の動きにも影響を与えることがあります。
思春期に差し掛かると見た目に対する意識が高まり、歯並びがコンプレックスになる場合もあるため、お子さまの精神面を考慮した上でケアすることが大切です。
もちろん、すべてのお子さまが将来大きな問題を抱えるわけではありませんが、歯並びの乱れが顕著な場合はできるだけ早い段階で専門家に相談することをおすすめします。
小児矯正のメリットと治療期間の目安
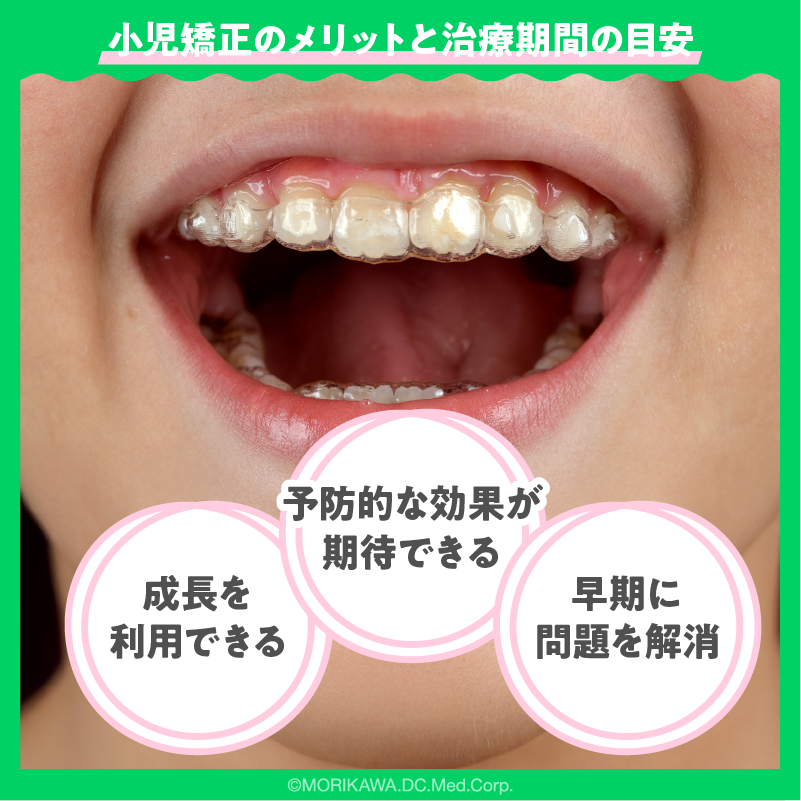
小児矯正のメリット
成長を利用できる
顎の成長期を活かして治療できるため、歯を抜かずにスペースを確保できる可能性が高い。
予防的な効果が期待できる
顎関節症や歯周病など、将来のリスクを軽減しやすい。
早期に問題を解消
虫歯リスクや発音不良、コンプレックスなどの問題を未然に回避しやすい。
治療期間の目安
小児矯正は、第一期(6〜7歳から10歳前後まで)と、第二期(12歳前後〜中学生以降)の二段階で行われることが多いです。
個人差がありますが、平均的には第一期が1〜2年程度、第二期が2〜3年程度かけて治療していくケースが一般的です。
また、お子さまの成長度合いや歯の生え変わりのタイミングによって治療期間が前後する場合もありますので、継続的な経過観察が必要です。
もりかわ歯科医院が考える最適な治療プランとは
「ママとこどものはいしゃさん」の特徴
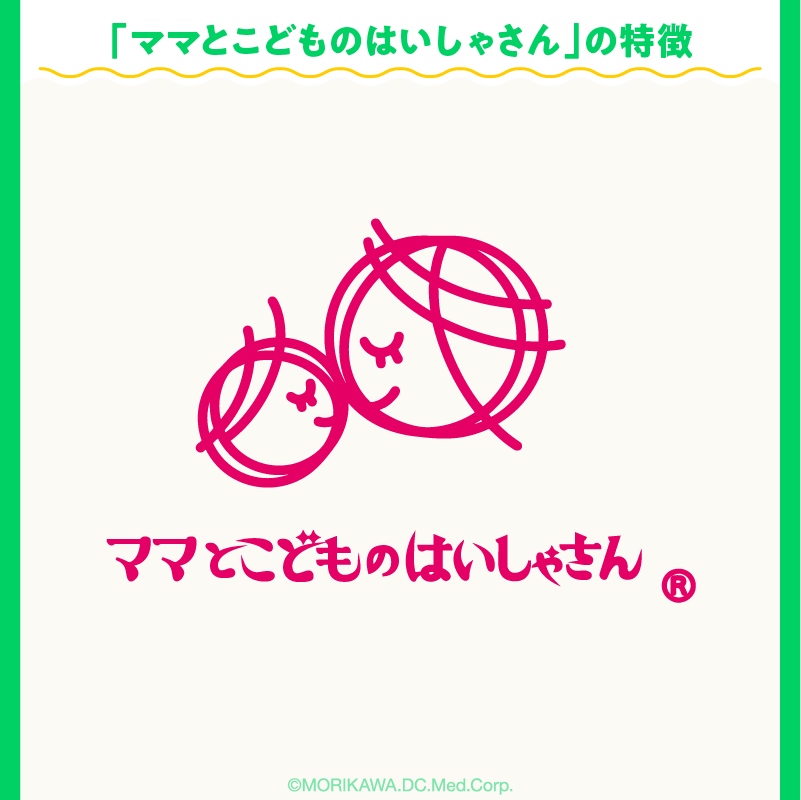
私たち「もりかわ歯科」では、小児歯科領域での豊富な知識・経験を活かし、お子さまと保護者の方の気持ちに寄り添う治療を心がけています。
特にお子さまは治療への不安が大きい場合もありますので、コミュニケーションを大切にして、痛みやストレスを最小限に抑えられるよう配慮しています。
カウンセリング〜治療までの流れ
1. カウンセリング・検査
はじめに、お子さまの歯並びや噛み合わせの状態を確認しながら、矯正が必要かどうかや治療の適性を判断します。
現状を正しく把握することで、必要な治療期間の目安や費用、保険適用の可能性を具体的にイメージしやすくなります。
さらに、支払い方法の選択肢についても丁寧にご説明し、保護者の方が抱えている不安を少しでも軽くできるように配慮します。
2. 治療方針の決定
お子さまの年齢や成長度合いに合わせて、第一期矯正と第二期矯正を含めた長期的なプランを組み立てます。
使う装置の種類や通院の頻度は、日常生活やお子さまの性格、保護者の方のご希望などを考慮した上で最適な提案を心がけています。
無理なく通える治療スケジュールを作ることで、継続して通いやすくなり、より効果的な矯正が期待できるでしょう。
3. 治療開始
具体的な治療が始まると、装置の装着や定期的な調整が必要になります。
お子さまが怖がらないように声かけやコミュニケーションを大切にしながら、痛みや不安をできるだけ抑える工夫をしています。
また、通院のたびに装置の状態やお口のクリーニングを行い、虫歯や歯肉炎などのトラブルが起きないようにチェックするのも重要なポイントです。
4. 保定・メンテナンス
矯正治療を終えて歯並びが整った後も、保定装置を使いながら並んだ歯を安定させる期間が必要です。
歯はどうしても元の位置に戻ろうとする性質があるため、定期健診で歯並びの変化を見守り、必要に応じて装置の調整などを行います。
こうしたメンテナンスをきちんと継続することで、きれいに整った歯並びを長く保つことができるのです。
費用と支払いの相談も柔軟に
もりかわ歯科では、治療前に費用の総額と内訳をしっかりお伝えし、ご希望に応じて分割払いやデンタルローンのご案内も可能です。
「費用負担が不安で…」という方でも、お気軽にご相談ください。
まとめ:早めの相談で子どもの未来をより豊かに
小児矯正の費用は決して安くはありません。
ですが、お子さまの将来の歯の健康やコンプレックスの解消を考えれば、早期対処のメリットは非常に大きいといえます。
また、保険適用が難しいケースでも、医療費控除の活用や分割払いなど、費用面の負担を軽減する方法はさまざまです。
「もう少し大きくなってからでもいいかな?」と悩んでいる方も多いと思いますが、成長期をうまく活かせるのは今だけです。放置すれば、歯並びによる噛み合わせ不良が将来的なトラブルにつながる可能性もありますし、治療期間や費用がかえって大きくなる場合もあります。
本記事で小児矯正に関する疑問は解消できましたでしょうか? 「まだ不安なことがある」「うちの子は本当に矯正が必要?」など、気になることがあれば、ぜひ一度歯科医院へ足を運んでみてください。私たち「ママとこどものはいしゃさん」もりかわ歯科では、まずはお子さまの成長段階をしっかり確認し、保護者の方のご希望に沿った最適な治療計画をご提案します。
歯並びは早めに対策するほど、良好な結果が得やすいといわれています。この記事が、小児矯正に対する不安を少しでも取り除き、お子さまの未来への第一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。ぜひお気軽に、私たちへご相談ください。