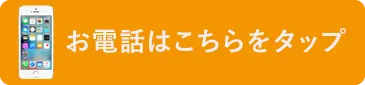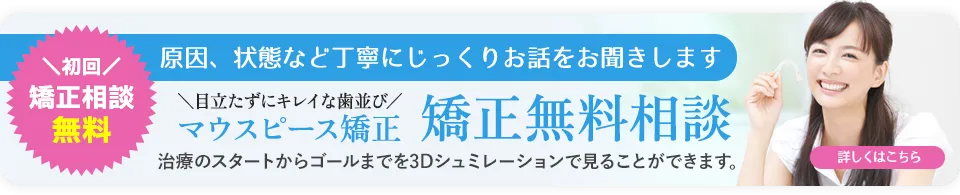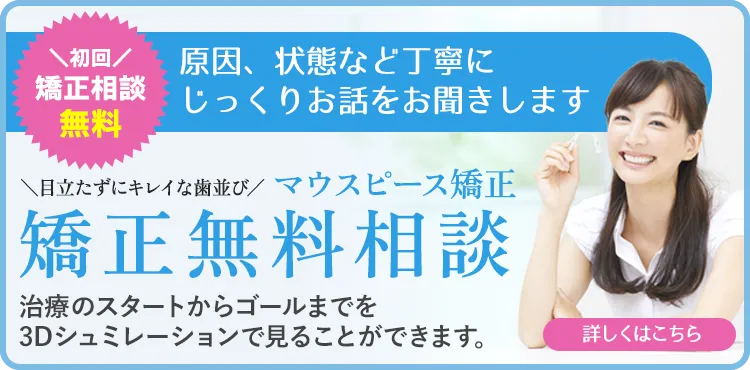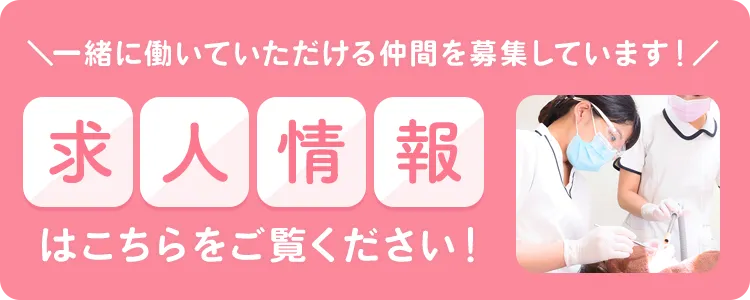こんにちは。大阪府八尾市にある医療法人甦歯会 もりかわ歯科です。
子どもの歯並びや噛み合わせに関する悩みのなかでも、受け口は特に注意が必要な状態のひとつです。見た目の問題だけでなく、成長とともにあごの骨格や発音、食事の仕方にまで影響を及ぼすことがあり、早期の発見と対処が重要です。
しかし、受け口の症状や原因、治療のタイミングについては、保護者の方でも正しく理解されていないことが多くあります。
今回は、子どもの受け口の原因や放置することのリスク、治療法などについて解説します。
Contents
受け口とは
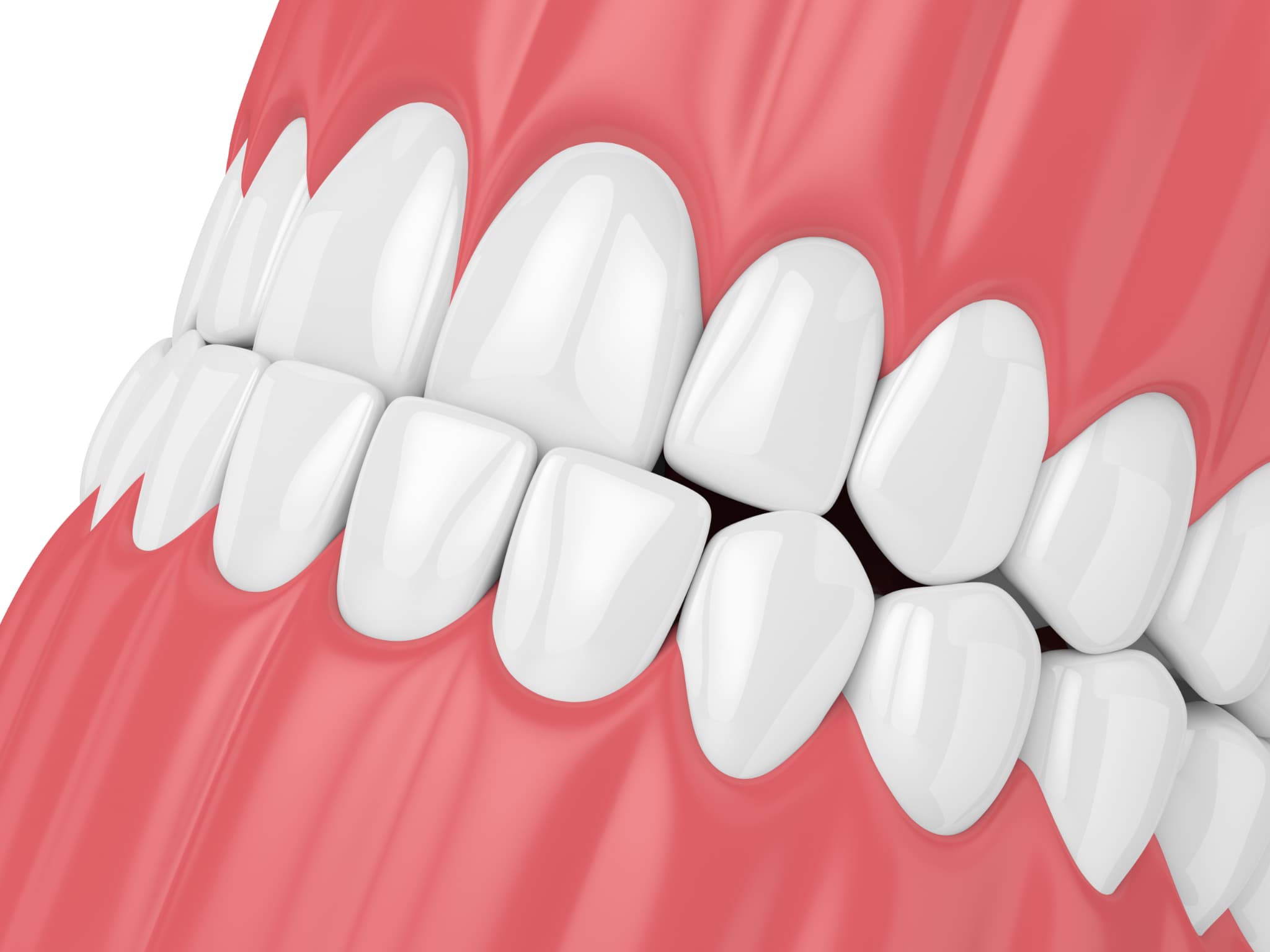
受け口とは、上下の前歯が通常とは逆に噛み合う状態を指します。医学的には、反対咬合(はんたいこうごう)や下顎前突(かがくぜんとつ)と呼ばれます。
通常は上の前歯が下の前歯より前に出ているものですが、受け口の場合は下の前歯が前に出ており、口元がしゃくれたように見えるのが特徴です。
このような噛み合わせは見た目の印象に影響するだけでなく、発音のしづらさや、食事の際にうまく噛めない、消化に負担がかかるなどの機能的な問題も引き起こします。
子どもの場合、あごの成長や歯並びの変化によって悪化することもあるため、単なる成長過程として放置せず、正しく対応することが大切です。
子どもの受け口の原因

ここでは、子どもが受け口になる原因について解説していきます。
遺伝的要因
受け口は、生まれ持った骨格や歯並びの特徴が関係することがあります。親から引き継ぐ顎の形や歯の位置の影響で、同じような症状が家族内で見られるケースも少なくありません。
このような遺伝的な要因は、生活習慣だけでは予防が難しいため、早めに歯科医院で診断を受けることが重要です。
成長発育の影響
顎の成長が不均衡であると、下顎が上顎よりも早く成長することがあり、これによって受け口を引き起こすことがあります。歯の生え変わりや顎の成長の過程で噛み合わせが変わってくることもあります。
生活習慣や癖の影響
生活習慣や口周りの癖も子どもが受け口になる原因のひとつです。
例えば、指しゃぶりや舌を突き出す癖があると、それが原因で受け口になることがあります。これらの習慣は、歯や顎の位置に直接影響を与え、長期間続くと噛み合わせに問題を引き起こす可能性があります。
受け口が及ぼす影響

ここでは、子どもの受け口が与える具体的な影響について解説していきます。
噛み合わせの異常
受け口は、下顎が上顎よりも前に出ている状態となるため、噛み合わせの異常を引き起こします。通常の状態では上下の歯が噛み合うことで食事ができますが、受け口の場合、食べ物をしっかりと噛み切ることが難しくなります。
このような異常は、食事の際の不便さだけでなく、成長過程であごの発達に影響を与えることもあります。
顔の見た目への影響
下顎が前に出ると、顔全体のバランスが崩れやすく、横から見たときの輪郭にも変化があらわれます。特に成長期の子どもにとっては、この変化が心理的な負担になることがあります。
発音への影響
舌の位置や動きが制限されることで、さ行やた行などの音が発しにくくなる場合があります。 これによって、話すときにストレスを感じたり、人前で話すことを避けたりするようになることもあります。
虫歯や歯周病のリスク
歯が重なっていたり、噛み合わせが悪かったりすると、歯磨きがしづらくなり、磨き残しが増えます。その結果、虫歯や歯周病のリスクが高まります。
子どもの受け口の治療法

子どもの受け口の治療は、顎の成長を利用できる5〜7歳ごろに始めるのが望ましいとされています。ここでは代表的な治療法をご紹介します。
予防矯正
乳歯や永久歯が混在している時期に行う治療で、口の周囲の筋肉バランスを整えることを目的としています。成長期に合わせて矯正することで、自然な発育を助けることが期待できます。
代表的な装置であるプレオルソは、柔らかい素材でできたマウスピース型の矯正装置で、就寝時と日中1時間程度装着することで、舌の位置や口呼吸の改善、顎の自然な成長を促します。痛みが少なく、取り外しも可能なため、幼児期の子どもでも無理なく使用できます。
床矯正
床矯正は、取り外し可能な拡大装置を用いて、顎の幅を広げる治療法です。
歯が並ぶスペースを確保することで、受け口の原因となる歯列の乱れを改善します。主に6〜10歳頃の混合歯列期に行われ、装置のネジを定期的に調整することで、少しずつ顎の幅を拡大していきます。お子さんへの負担が少なく、ご家庭での管理が可能な点も特徴です。
フェイスマスク
骨格的な受け口に対しては、フェイスマスクと呼ばれる外部装置を使用することがあります。これは、上顎の成長を前方に促すための牽引装置で、主に夜間に装着します。
上顎の成長が遅れている場合や、下顎の突出が強い場合に適応され、骨格のバランスを整えることで、自然な噛み合わせを目指します。一定時間装着する必要がありますが、成長期の骨格修正に有効です。
ワイヤー矯正
永久歯が生え揃ったあとに行われる本格的な矯正治療が、ワイヤー矯正です。歯にブラケットと呼ばれる装置をつけ、そこにワイヤーを通して歯を少しずつ理想的な位置に動かしていく治療法です。歴史が長く、多くの症例に対応できる点が特徴です。
受け口のように噛み合わせの調整が複雑な場合でも、細かなコントロールがしやすく、高い効果が期待できます。
一方で、装置が目立ちやすい点や、食事や歯磨きがしにくい点には注意が必要です。
マウスピース矯正
マウスピース矯正とは、取り外し可能な装置を使用して歯並びを整える方法です。使用する装置は透明であるため、装着していても目立ちにくいことから多くの方に選ばれています。また、矯正をはじめる前と同じように食事や歯磨きができるため衛生的です。
受け口を矯正するメリット

受け口を早めに治療することで、見た目の改善だけでなく、さまざまなメリットが得られます。
たとえば、あごの骨の成長を正しい方向へ導くことができ、顔のバランスが整いやすくなります。これにより、将来的な見た目のコンプレックスを減らすことができ、自信を持って人と接することにもつながります。
また、発音や咀嚼(そしゃく)の機能が改善されることで、日常生活の質も大きく向上します。しっかりと噛めるようになれば消化も助けられ、体全体の健康にも良い影響があります。
発音が明瞭になることで、学校での発表や友達との会話に自信が持てるようになるお子さんも多くいます。
さらに、正しい噛み合わせを獲得することで、大人になってからの歯の摩耗や顎関節症といったトラブルを防ぐことにもつながります。受け口の早期治療は、子どもの心と体の健やかな成長を支えるための、大切な一歩と言えるでしょう。
受け口を矯正するときの注意点

受け口の矯正治療を始めるにあたっては、いくつか注意しておきたい点があります。まず、矯正は短期間で効果が出るものではなく、あごの成長とともに段階的に進めていく治療です。そのため、継続的な通院と根気強いケアが必要になります。
特に装置に慣れるまでは、子どもにとって違和感を覚えることもあるため、保護者の方のサポートがとても大切です。就寝中に装着するタイプの装置などは、慣れるまでに時間がかかることがあります。
子どもが前向きに治療に取り組めるよう、励ましながら進めていくことがポイントです。
また、矯正中は装置の影響で汚れがたまりやすく、虫歯や歯肉炎のリスクが高まります。普段よりも丁寧な歯磨きが求められますので、口腔ケアの指導も大切です。
さらに、使用する装置や治療方針、費用については事前にしっかりと説明を受け、納得したうえで治療を始めることが大切です。
まとめ

子どもの受け口は、見た目の問題だけでなく、さまざまな悪影響を及ぼす可能性があるため、放置せず、早めに治療を検討することが大切です。
成長期に適切な対応を行えば、顎の自然な発育を促し、将来の外科手術や大掛かりな矯正治療を避けられる可能性があります。
治療法にはいくつかの選択肢があり、それぞれに特徴や注意点があります。歯科医師による診断を受けることで、お子さまに合った治療法を選ぶことができます。
お子さまの歯並びや噛み合わせが気になる場合は、早めに歯科医院で相談してみましょう。
小児矯正を検討されている保護者の方は、大阪府八尾市にある歯医者「医療法人甦歯会 もりかわ歯科」にご相談ください。
当院では、虫歯・歯周病治療をはじめ、矯正治療や入れ歯・ブリッジ・インプラント治療、予防歯科などさまざまな診療を行っています。ホームページはこちら、ご予約・お問い合わせも受け付けております。