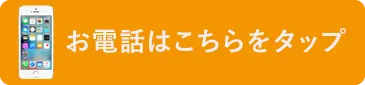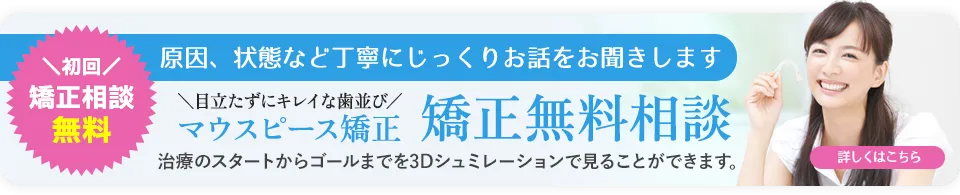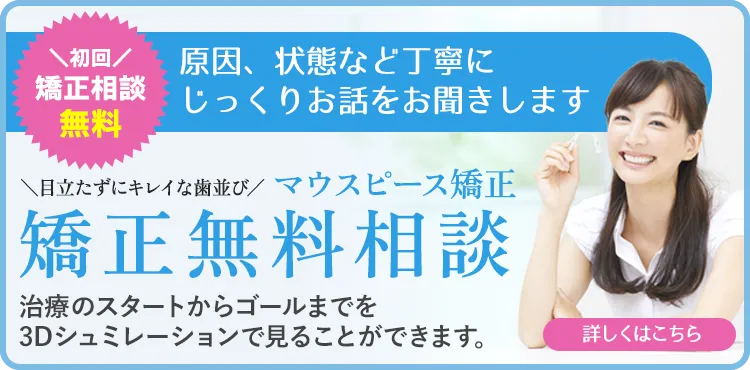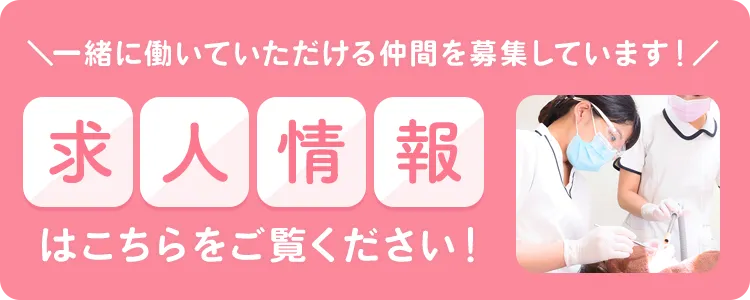こんにちは。大阪府八尾市にある医療法人甦歯会 もりかわ歯科です。
「子どもの歯科検診っていつから受ければいいの?」と疑問に感じている方もいるかもしれません。乳歯は永久歯に比べて虫歯になりやすく、虫歯が進行しやすいといわれています。そのため、乳歯が生え始めた赤ちゃんの時期から検診を受けることが推奨されています。
今回は、歯科検診を受ける年齢や検査内容、費用と頻度、子どもの歯科検診のメリット・デメリットなどについて解説します。
子どもの歯科検診は何歳から?

赤ちゃんの歯は生後6ヵ月程度で生え始めます。そのため、この時期に歯科検診を受け始めるよう推奨されています。1歳を過ぎるころには上下の歯が生え揃うため、噛み合わせの確認も行っていきます。
「0歳のうちから歯医者さんは早いのでは?」と感じる保護者の方も多いかもしれませんが、早期に始めることにより将来的な歯の健康にも繋がるでしょう。
子どもの歯科検診が重要な理由
なぜ子どもの歯科検診が重要なのでしょうか。以下では、子どもの歯科検診が重要な理由について解説します。
虫歯を早期発見・治療できる
乳歯は、永久歯に比べて薄くて柔らかいという特徴があります。歯質自体が弱いため、一度虫歯になると進行するスピードが早いのです。
「乳歯はいずれ永久歯に生え変わるから虫歯になっても問題ない」と考える方もいますが、乳歯の虫歯を放置すると永久歯の形や色にも影響を及ぼすことがあります。それ以外も、虫歯を放置すると歯並びや顎の発達に影響が出ることも考えられるでしょう。
特に、子どもの場合には自覚症状があまりないことや、痛みや違和感を言葉で伝えられないことから、重症化しやすいといえます。定期的な歯科検診により、早期発見・治療を行うことが重要なのです。
正しい口腔ケアを身につけられる
早い段階から歯科医院に慣れ、正しいケアを身につけることは、将来的な歯の健康の土台を築く上でも重要です。定期検診では、成長段階に応じてお口の状態に合ったセルフケア方法を指導します。
特に、成長期のお子さまの場合、常にお口の状態が変化していきます。同じ方法でケアを続けていると磨き残しが発生する可能性が高いでしょう。定期的にチェックすることは、非常に意義のあることといえます。
子どものうちから定期検診やセルフケアを当たり前のこととして受け入れられると、大人になってからも適切なケアを続けられます。
口内の異常を早期に発見できる
子どもの歯並びは、乳歯から永久歯に生え変わる時期に悪化し始めることがあります。
歯並びの乱れは見た目だけの問題ではなく、顎の発達や噛み合わせに影響を及ぼすことが考えられます。また、歯並びが乱れて歯磨きがしにくくなった場合、虫歯や歯周病のリスクも高まるでしょう。
小児期の矯正治療は、乳歯と永久歯が混在している時期に始めることが望ましいです。早期に発見すれば、スムーズに矯正治療に進むことも可能です。
子どもの歯科検診の検査内容

では、子どもの歯科検診ではどのようなことを行うのでしょうか。以下では、歯科検診で行う検査や処置の内容について解説します。
磨き残しの確認
子どもの歯科検診では、歯科医師や歯科衛生士がお子さまの口の中の状態を丁寧にチェックします。磨き残しやすい部分があると虫歯のリスクが高まるため、ブラッシングが不十分な箇所やブラッシングの癖などをチェックすることが重要です。
虫歯の有無の確認
歯科検診では、虫歯ができていないかも確認します。乳歯は虫歯の進行スピードが速いため、早期に発見・治療を行うことが大切です。
虫歯が見つかった場合には、穴が開いていない初期虫歯であればフッ素を塗布して様子をみることになるでしょう。すでに穴が開いているような場合には、虫歯を削って詰め物をすることもあります。
噛み合わせの確認
子どもの歯科検診では、噛み合わせのチェックも行います。特に、奥歯の噛み合わせが合っていない場合には、将来的に歯並びが乱れたり噛み合わせに問題が生じたりすることがあります。
早期に噛み合わせや歯並びの問題を発見できれば、顎の成長を利用した矯正治療も可能です。
レントゲン検査
目視だけでは確認が難しい場合には、レントゲン検査を行うこともあります。特に、乳歯から永久歯へ生え変わる時期には、乳歯の下にある永久歯が正しい方向で生えてくるかを確認することもあります。
将来的に生えてくる永久歯の向きや位置はもちろん、永久歯が存在しない先天性欠損の早期発見も可能です。
食生活の確認
子どものお口の中の健康と食生活は大きく関わっています。特に、糖分を多く含む食品を多く摂っている場合は、虫歯菌のエサとなるため食生活の改善が必要です。
虫歯を恐れて食事を制限すれば、子どもの成長に悪影響を及ぼす可能性もありますので適切な食事の摂り方を知ることが重要です。お子さまの食生活について気になることや不安なことがあれば、歯科医師や歯科衛生士にご相談ください。
クリーニング
子どもの歯科検診では、歯のクリーニングも行います。クリーニングでは普段の歯磨きでは落としきれない汚れや歯垢などを丁寧に取り除きます。
毎日しっかり磨いているつもりでも磨き残すことはありますので、定期的なクリーニングが非常に重要です。
歯磨き指導
歯科検診で行った検査の結果をもとに、適切な歯磨きの方法を指導します。磨き残しやすい部分や歯磨きの癖を知り、正しい方法を確認することで自宅でのケアもしやすくなるでしょう。
フッ素塗布
乳歯は永久歯よりも歯質が弱いため、定期的にフッ素を塗布して歯質を強化することも重要です。フッ素の効果が持続する期間は3ヵ月~4ヵ月ですので、定期的にフッ素を塗布しましょう。
子どもの歯科検診の費用と頻度

「子どもの歯科検診ってどのくらいの費用がかかるの?」「何度も通わないといけないの?」と疑問に感じている方もいるのではないでしょうか。ここからは、子どもの歯科検診の費用と頻度についてみていきましょう。
子どもの歯科検診の費用
子どもの歯科検診では、自治体の医療費助成が受けられることが一般的です。風邪などで小児科を受診するときと同様に、保険証と医療費助成証明書を持っていけば、負担額を軽減できます。
実際の負担額は自治体によって異なりますので、お住まいの地域で確認するようにしましょう。なお、子どもの歯科受診であっても、中には医療費助成が受けられない治療や処置もあります。
例えば、染め出し剤を用いたブラッシング指導や、虫歯予防のためのシーラント処置などは適用外となることもありますので、詳しくは歯科医院へご確認ください。
子どもの歯科検診の頻度
子どもの歯科検診の頻度の目安は、3ヵ月~4ヵ月に1回程度といわれています。虫歯や歯周病の原因となる歯石やバイオフィルムが形成されるのに3ヵ月~4ヵ月かかるためです。
歯石やバイオフィルムは、一度形成されると通常の歯磨きで取り除くことが難しくなります。そのため、歯科医院で専用の機器や器具を用いて取り除く必要があります。
歯石やバイオフィルムが形成されてしまっても、この頻度で歯科検診を受けていれば早期に対処が可能です。また、歯科検診ではフッ素塗布を受けることがありますが、フッ素の効果が持続する期間も3ヵ月~4ヵ月といわれています。
それ以上経過するとフッ素の効果が切れてしまいますので、定期的にフッ素を塗布することが大切です。
子どもの歯科検診のメリット・デメリット

最後に、子どもの歯科検診のメリット・デメリットについて確認しましょう。
子どもの歯科検診のメリット
子どもの歯科検診のメリットは、虫歯の早期発見・治療ができることです。乳歯は虫歯になりやすく進行スピードも速いため、定期的にチェックすることが虫歯の予防にも役立ちます。
また、早いうちから適切なケアを身につけることで、将来的な虫歯のリスクも軽減できるでしょう。そのほか、成長段階では噛み合わせや顎の成長具合も変化しますので、何か問題が生じた場合でも早期に対処できるというメリットもあります。
子どもの歯科検診のデメリット
子どもの歯科検診は虫歯の予防や早期発見に役立ちますが、デメリットも存在します。歯科医院は、初めてのお子さまにとっては恐怖や不安を感じやすい場所でもあります。
医薬品の独特なにおいや医療機器、マスクを着けた歯科医師や歯科衛生士など、慣れない場所が苦手な赤ちゃんにとってはストレスになることがあります。この場合、少しずつ慣らしていく必要があるでしょう。
赤ちゃんや小さなお子さまの場合、痛みを伴うような治療をすることはほとんどありませんが、歯科医院がトラウマになる可能性もあります。子どもが安心して通えるような雰囲気の歯科医院を選ぶことも大切です。
まとめ

早いうちから歯科検診を受けることは、虫歯の早期発見や早期治療はもちろんですが、将来的な歯の健康維持にも役立ちます。特に、乳歯のうちは虫歯になりやすく進行スピードも速いため、定期的にチェックを続けていきましょう。
「検診を受けたいけれど赤ちゃんが泣くかもしれない」「子どもの歯の相談をしたいけれど初めてだから不安」という方も、まずは一度ご気軽にご相談ください。
お子さまの歯科検診を検討している方は、大阪府八尾市にある歯医者「医療法人甦歯会 もりかわ歯科」にご相談ください。
当院では、虫歯・歯周病治療をはじめ、矯正治療や入れ歯・ブリッジ・インプラント治療、予防歯科などさまざまな診療を行っています。ホームページはこちら、ご予約・お問い合わせも受け付けております。