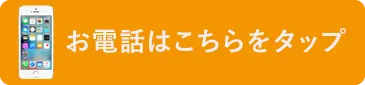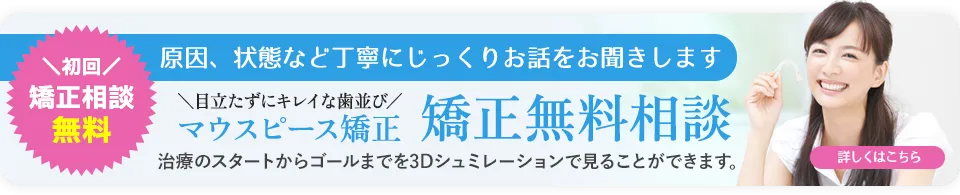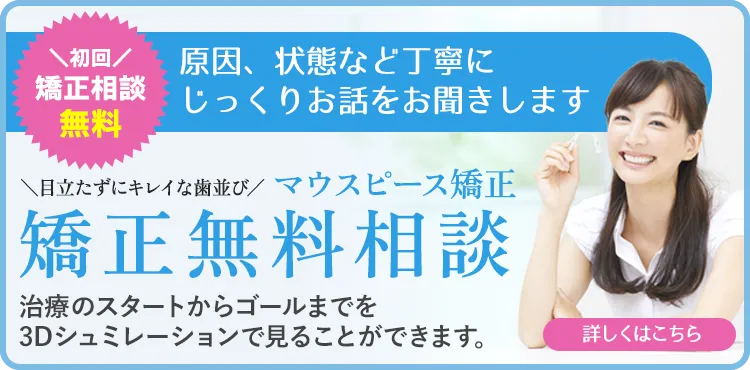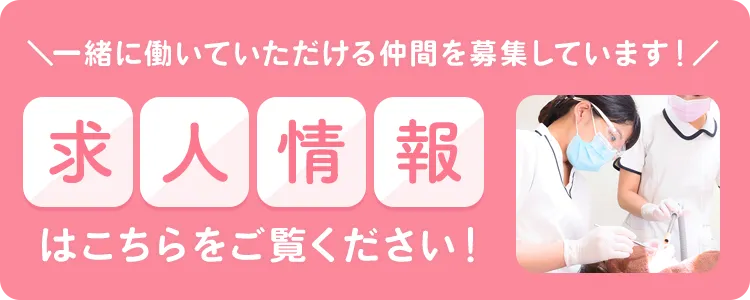こんにちは。大阪府八尾市にある医療法人甦歯会 もりかわ歯科です。
歯と歯の間にできる虫歯は、見た目では気づきにくく、痛みが出る頃には進行しているケースが少なくありません。このタイプの虫歯は隣接面う蝕と呼ばれます。進行すると治療が複雑になり、歯の神経にまで影響を及ぼすこともあります。
この記事では、歯と歯の間に虫歯ができる原因や、見逃さないためのポイント、治療方法について詳しく解説します。
歯と歯の間に虫歯ができる原因

ここでは、歯と歯の間に虫歯ができる主な原因について詳しく解説します。
磨き残しによるプラークの蓄積
歯と歯の間は歯ブラシの毛先が届きにくく、プラークが蓄積しやすい場所です。プラークは細菌のかたまりであり、糖分を栄養源として酸を産生し、歯の表面を溶かします。このため、歯と歯の間にプラークが残った状態が続くと、虫歯のリスクが高まります。
通常のブラッシングだけではこの部位のプラーク除去が不十分になりやすいため、デンタルフロスや歯間ブラシの併用が不可欠となります。
間食や甘い飲食物の頻繁な摂取
間食の回数が多かったり、糖分を多く含む食品や飲み物を頻繁に摂取したりする習慣も、隣接面の虫歯リスクを高める要因となります。口腔内が酸性に傾く時間が長くなると、歯の表面が脱灰しやすくなり、虫歯の進行が促されます。
特に、砂糖入りの飲み物を長時間かけて飲む習慣は、歯と歯の間の汚れが流されにくく、虫歯を誘発しやすくなるため注意が必要です。
不適切な歯並びや接触面の異常
歯並びが悪く、歯と歯の間に隙間ができていたり、逆に強く接触していたりすると、歯間清掃が難しくなりプラークがたまりやすくなります。また、詰め物や被せ物が合っていない場合も、段差にプラークが停滞しやすく、隣接面虫歯のリスクを高める原因になります。
矯正治療や補綴物の適切な調整によって、歯と歯の間の清掃性を改善することが虫歯予防には重要です。
唾液の減少
唾液には、口腔内を洗浄し、細菌の活動を抑える働きがあります。
しかし、ストレスや加齢、薬の副作用などによって唾液分泌が減少すると、口腔内の自浄作用が低下し、虫歯リスクが高まります。特に、歯と歯の間のような細かい部分では、唾液による清掃効果が期待できなくなるため、より丁寧なセルフケアが求められます。
歯と歯の間に虫歯ができていないか確認する方法

歯と歯の間にできる虫歯は、表面からは見えにくいため、自覚症状が出るまで気づかないことが少なくありません。初期段階で発見できれば、治療の負担を最小限に抑えることができるため、日常的にセルフチェックを行いましょう。
ここでは、歯と歯の間に虫歯ができていないかを確認するための方法について解説します。
デンタルフロスを活用する
セルフチェックで効果的なのが、デンタルフロスを使用する方法です。フロスを歯と歯の間に挿入し、スムーズに通らない箇所がないか確認します。引っかかりやザラつきを感じた場合、表面が荒れている可能性があり、虫歯や初期脱灰が進行しているサインかもしれません。
見た目や感覚の変化に注意する
歯と歯の間に虫歯ができると、食べ物が詰まりやすくなったり、冷たいものや甘いものにしみたりすることがあります。これらの感覚の変化は、隣接面虫歯の初期症状である場合があります。
また、鏡で歯の間を観察したときに、歯の色が暗くなっている、あるいはわずかに欠けている箇所が見える場合にも注意が必要です。違和感がある場合は、早めに歯科医院を受診しましょう。
定期的な歯科検診でチェックする
セルフチェックだけでは限界があるため、定期的な歯科検診を受けることが欠かせません。歯科医師によるプロフェッショナルな検査では、レントゲン撮影を用いて歯と歯の間の虫歯を早期に発見できます。
自覚症状がない段階でも異常を捉えることができるため、虫歯が小さいうちに適切な処置が可能です。
歯と歯の間の虫歯を治す方法

ここでは、歯と歯の間の虫歯を治療する方法について解説します。
初期段階での対応
歯と歯の間に初期の虫歯が認められる場合、すぐに削らず経過観察となることもあります。歯の表層であるエナメル質内に限局している場合には、再石灰化によって進行を抑えることができるため、フッ素塗布やフッ素入り歯磨き粉の使用が推奨されます。
定期的な歯科検診で経過を観察しながら、セルフケアを徹底することが重要です。この段階で適切な対応ができれば、歯を削らずに改善できる可能性もあります。
穴が開いた場合の治療
虫歯が進行し、歯と歯の間に明らかな穴が開いた場合には、削って修復する必要があります。まず虫歯に侵された部分を最小限に取り除き、その後、歯と歯の間に適したコンポジットレジン(歯科用プラスチック)で詰める治療が行われます。
コンポジットレジンは色調を歯に合わせることができるため、審美性にも優れています。虫歯の進行が浅い段階であれば短時間で治療が完了し、負担も軽減されます。
深部まで進行した場合の治療
虫歯がエナメル質を越えて象牙質に達し、さらに歯の神経(歯髄)まで炎症が及んでいる場合には、根管治療(根っこの治療)が必要になります。
根管治療では、感染した神経や血管を取り除き、内部をきれいに清掃・消毒した後に薬剤を詰め、密閉します。その後、被せ物(クラウン)によって歯全体を補強する処置が施されます。この段階に進行すると治療期間も長くなり費用も高額になるため、早期発見の重要性が際立ちます。
歯と歯の間に虫歯ができるのを防ぐには

歯と歯の間にできる虫歯を未然に防ぐためには、日頃から意識して口腔ケアに取り組むことが重要です。ここでは、歯と歯の間の虫歯予防に効果的な方法について解説します。
デンタルフロスや歯間ブラシを使う
歯と歯の間は、通常の歯ブラシだけではプラークを十分に除去することが難しい部位です。このため、デンタルフロスや歯間ブラシを併用することが予防には不可欠です。
デンタルフロスは、歯と歯の接触面にぴったり入り込み、プラークや食べかすを効果的に取り除くことができます。歯間ブラシは、歯と歯の間に少し隙間がある場合に有効で、より広い範囲の清掃に効果的です。
毎日のブラッシングに加えて、フロスや歯間ブラシを使う習慣をつけることで、隣接面虫歯のリスクを大幅に下げられます。
フッ素を積極的に取り入れる
フッ素には歯の再石灰化を促進し、初期の虫歯を修復する働きがあります。日常的にフッ素入りの歯磨き粉を使用することで、歯質を強化し、虫歯に対する抵抗力を高められます。
また、歯科医院で定期的にフッ素塗布を受けると、さらに高い予防効果が期待できます。特に、隣接面は汚れがたまりやすく酸にさらされる時間が長くなるため、フッ素による保護は非常に有効です。
食生活を見直す
虫歯菌は、糖分を餌にして酸を作り出し、歯を溶かしていきます。そのため、甘いものを頻繁に摂取する習慣は虫歯リスクを高めます。間食の回数を減らし、甘い飲み物やお菓子を控えることが大切です。
また、食後はできるだけ早めにブラッシングを行うか、難しい場合にはうがいをして口腔内を清潔に保つことを心がけましょう。規則正しい食生活は、虫歯だけでなく、口腔全体の健康維持にもつながります。
定期的な歯科検診を受ける
自分では見つけにくい隣接面の虫歯を早期に発見するためには、定期的な歯科検診が欠かせません。歯科医院では、プロフェッショナルなクリーニングで歯と歯の間の汚れを徹底的に除去できるだけでなく、レントゲン撮影によって目に見えない虫歯の兆候もチェックできます。
早期に発見できれば小さな処置で改善でき、歯を大きく削るリスクも抑えることができます。一般的には3か月から6か月ごとの受診が推奨されています。
唾液の分泌を促進する
唾液には、口腔内の細菌を洗い流し酸を中和する働きがあります。ストレスや加齢、薬の副作用などで唾液の量が減少すると、虫歯のリスクが高まります。唾液分泌を促すためには、よく噛んで食事をとること、水分をこまめに摂取することが有効です。
また、キシリトール入りのガムを噛むことも唾液分泌を促進する手軽な方法の一つです。
まとめ

歯と歯の間にできる虫歯は隣接面う蝕と呼ばれ、ブラッシングだけでは汚れを取り除きにくく、発見が遅れやすいのが特徴です。磨き残しや食生活の乱れ、歯並びの問題、唾液量の減少などが主な原因となります。
セルフチェックにはデンタルフロスの活用が有効ですが、早期発見には定期的な歯科検診が不可欠です。予防にはフロスや歯間ブラシを取り入れたケア、フッ素利用、食生活の見直しが重要です。虫歯ができた場合は進行度に応じた適切な治療を受けることが大切です。
歯と歯の間の虫歯でお悩みの方は、大阪府八尾市にある歯医者「医療法人甦歯会 もりかわ歯科」にご相談ください。
当院では、虫歯・歯周病治療をはじめ、矯正治療や入れ歯・ブリッジ・インプラント治療、予防歯科などさまざまな診療を行っています。ホームページはこちら、ご予約・お問い合わせも受け付けております。